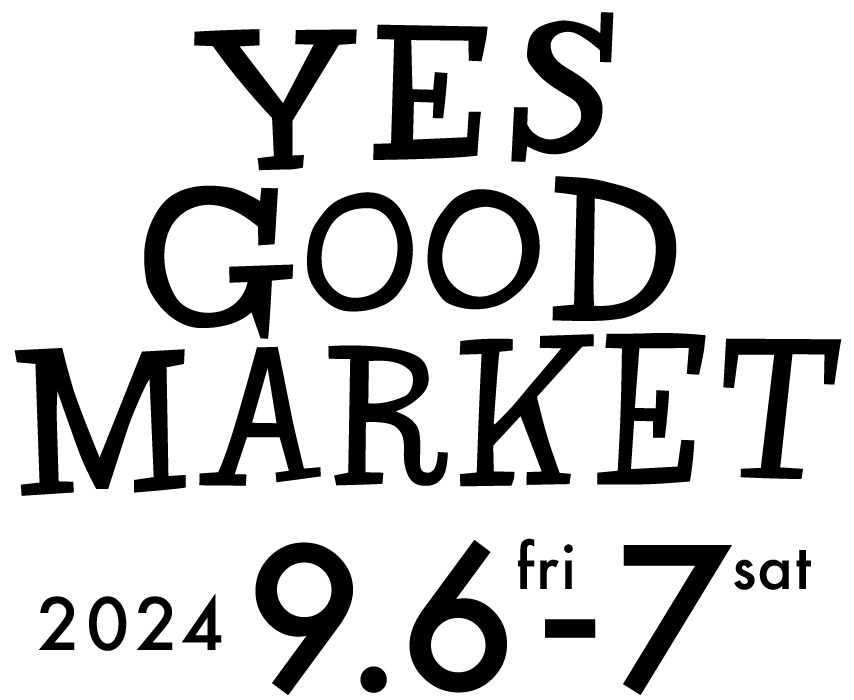2016年にスタートしたYES GOOD MARKET(以下、YGM)も今年で9回目。これまでは静岡で開催してきたが、今回はその拠点を京都に移動。なぜ?という率直な疑問を、イベントを主催するSEE SEEのディレクター湯本さんと、去年から運営のサポートに入ったURBSのディレクター村手さんにぶつけてみたら、話は原点回帰へ。YGMの本質がグッと見えてきた。
湯本弘通
ゆもと・ひろみち。伝統工芸である静岡挽物を継承する、HOMEWAREブランド「SEE SEE」ディレクター。2016年、新しいマーケットとして「YES GOOD MARKET」をスタート。2020年からは、不規則なバランスをコンセプトとした「Stripes For Creative」のディレクションも手掛けている。
村手謙介
むらて・けんすけ。アーバンリサーチのクリエイティブディレクター兼バイヤー統括、URBS(URBAN RESEARCH BUYERS SELECT)ディレクター。1979年生まれ。学生の頃からアーバンリサーチに勤務し、店長を経て現職。厳選された逸品の一品を集めるという、セレクトショップの原点回帰をコンセプトに掲げる「URBS」は幅広い層から支持を集める。
その土地ならではのコミュニティを作りたい。

ーまず最初に、お二人の出会いについて教えてください。
村手:会社としては、2020年にYGMにオンラインで参加したのが最初で、個人的には4年ほど前から。湯本さんがディレクションしているSFC(Stripes For Creative)をURBSでお取り扱いさせていただいていて、そのタイミングでSEE SEEとも一緒に何かできないかという話になって、そこから始まった感じです。
ーお互いの印象についてはどうですか?
湯本:大手なんですけど、大手っぽくないところが好きなんです。
村手:正直、僕らみたいなセレクトショップって、コロナ前ぐらいから、どこのお店も同じ品揃えみたいな、そんな流れを感じていました。一方で、海外出張でいろんな国を見ていると、インディペンデントなコミュニティがたくさんできていくのを目の当たりにして。日本もコロナのタイミングで少しはできてきましたが、その中でも湯本さんはいち早く取り組まれていた気がします。なので、どうやってやっているのか単純に興味がありました。
ーそもそもYGMをやろうと思ったきっかけや原体験は何でしょうか?
湯本:僕も10年くらい前、サンフランシスコによく行っていたのですが、当時からスモールコミュニティがポツポツでき始めていて、それがとてもカルチャーショックで。いわゆるインディペンデントなブランドやサードウェーブのコーヒーショップがそうです。それから僕も友達同士でいいものを表現し合って、コミュニティを作っていきたいと思うようになって。東京と静岡って近いじゃん! みたいなところから、東京のかっこいいなって思う人たちを誘って、普段雑誌でしか会えない人たちが対面で接客してくれたら、お客様も喜んで頂けそうだし面白いなと思って、YGMを始めました。
はっきりしてきた“YGMらしさ”の輪郭。

ーこれまでの出店者を見ると、ファッションだけでなく、フードに関しても同じような目線を感じます。
湯本:いわゆるメジャーではなく、クラフトビールやナチュラルワインだったり、本当に小さい規模でやっているかっこいい人たちを集めています。今でこそサポートしてくれる人がいますけど、最初の頃はめちゃくちゃ大変でした。それこそ会場の図面も全部一人で測って、出店者全員に連絡して。手作り感満載でした。そこから、ケンちゃん(施工チームの代表)に美術的なところをお願いするようになってから、視覚的にも楽しんでもらえるようになって、一気に広がった気がします。
ーYES GOOD MARKETのネーミングはどのように?
湯本:最初は、アーロン・ローズの映画『BEAUTIFUL LOSERS』が大好きなこともあり、反逆精神を込めて「LOSERS MARKET」がいいなぁなんて考えていました。でも、ちょっとカルチャー感が強いかもという話になって、ちょうどインスタが注目され始めたタイミングもあり、“いいね!”を押す、“GOOD!”を押すという流れから、YES GOOD MARKETになりました。結果、定着して良かったです。
ー改めて、YES GOOD MARKETのコンセプトというのは?
湯本:「非日常のショッピングを楽しめる空間」です。大げさに言えばここをディズニーランドのテーマパークに変えてしまうようなイメージ。もちろん、それを実現するためには施工チームの力が欠かせません。ただ、毎回時間をかけて構想を練って頑張って作ったものを、たった2日間で全部壊してしまうのが名残惜しいですけど(笑)。
そこにYGMがあれば、非日常を味わえる。

ーこれまではずっと静岡で、今回初めて京都での開催となります。これにはどんな経緯が?
湯本:まだ言えないのですが、この先に控えている大きなプロジェクトがありまして、そこにしっかり繋げていきたいという思いもあり、いろんなタイミングが重なってこの場所(京都)になりました。ただ、京都は僕らからするとお邪魔させていただいている感覚なので、軸は静岡に置きつつも、そこに属するコミュニティに対して、ちゃんとリスペクトの気持ちを持ったマーケットイベントにしたいという思いの方が強いです。
ーそれでいうと、京都を皮切りにいろんな場所で開催していく予定があるんですか?
湯本:まさに、移動式でいいのかなっていう考えもあります。それこそ、国内だけじゃなくて海外の可能性もあるかもしれないですし。YGMは身軽でいいんです。その時の感覚で、いいと思ったらやろうぜ!っていうノリの良さが大事。その土地や住んでいる人たちに敬意を払いつつ、面白いことをローカルコミュニティとして作って、都度発信していけたら、YGMはもっと面白くなっていくのかなと思っています。
ーアーバンリサーチが運営をサポートするのは今回が2回目。前回で得た気づきなどはありますか?
村手:去年は全体のチームを含め、湯本さん主導で進めた部分が大きかったんですけど、今回はうちの若手をたくさん入れていて、育成にも繋げています。それこそ、京都の作家さんと繋がってる子たちが出すブースもあるんです。やっぱり社員教育的なところで、次世代の子たちにもYGMを深く知ってもらって、内輪から盛り上げたいというか、空気感を感じてもらいたいという思いがあります。

ーメインビジュアルもYGMらしさ全開で素敵です!
湯本:今回初めての京都ですし、京都の風景を撮ってそれにロゴを入れて、もう少しメジャー感のあるビジュアルに変えていこうかみたいな話があったんですけど、やっぱり僕ららしくないなって。それで以前から好きだった高岡周策さんにお願いしました。実は、これも当初手が中指を立てているビジュアルだったんですけど、指をハートに変えることで、来場者を含め、YGMに関わるすべての人たちがハッピーになってほしいという思いを込めました。

ー今回ならではの見どころがあれば!
湯本:ファッションだけじゃなくて、例えば、関東と関西の食べ比べや飲み比べなど、実際に会場に来ないと体験出来ない、京都ならではの切り口を色々と仕込んでいるので楽しみにしていてください。
村手:とにかく気持ちいい場所にあります。周辺には平安神宮や国立近代美術館とか、京都ならではの文化的施設もたくさんあるので、2日間通して楽しんでいただけるはずです。会場で是非お待ちしています。
Photo:Asami Nobuoka
Text:Jun Nakada